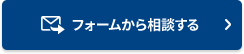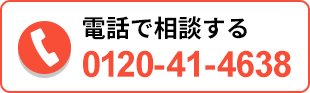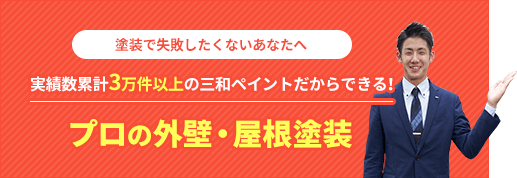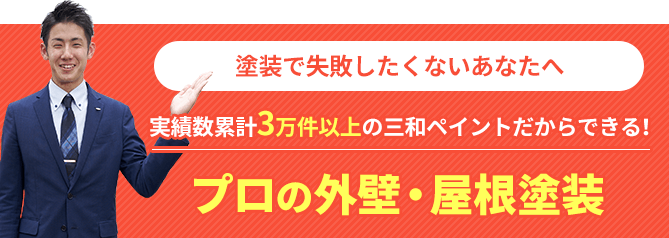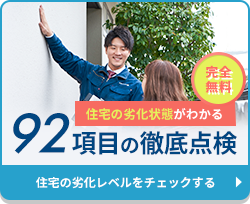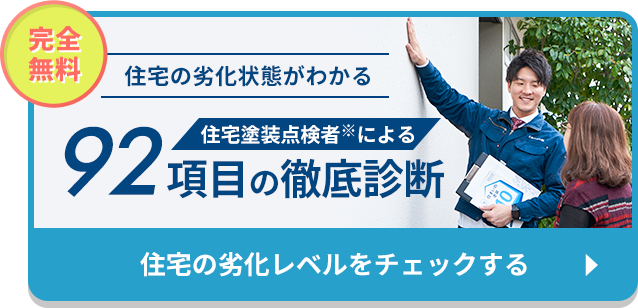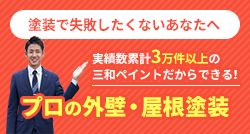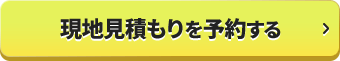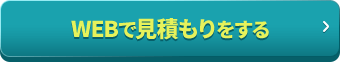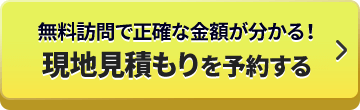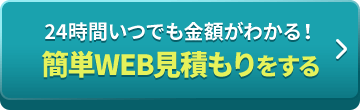屋根のメンテナンス方法
本項では屋根のメンテナンス方法を解説していきます。
屋根と一口に言っても屋根材に使われている素材や屋根の種類、お住まいの地域の気候によって劣化スピードや最適なメンテナンス方法が異なります。
スレート屋根に発生する症状とメンテナンス方法

スレート屋根は現在の日本の新築戸建で多く採用されている屋根材のひとつです。
以前から使用されていたメーカーの商品名から「カラーベスト」や「コロニアル」と呼ばれることも少なくありません。
スレート屋根は軽量かつ安価なため、地震の多い日本では倒壊リスクを抑えることができて安心です。
屋根材のひび割れ
スレート屋根は軽量が故に厚さはだいたい5mm程度と薄く、衝撃には弱いというデメリットがあります。
経年劣化はもちろん、台風の時期には強風で飛来したものが屋根にぶつかり、衝撃でひび割れてしまうこともあり、破損に気づかずに放っておくと雨漏りなどの原因になり、最悪の場合はスレート屋根自体の腐食が進んでしまいます。
また、雨水による湿気と直射日光による乾燥を繰り返すことによる屋根材の反りも薄いスレート屋根では発生しやすい症状のひとつです。
ひび割れが軽度なものであればコーキング材を用いて補修を行うことも可能で、補修箇所の大きさや数によっても違いはありますが、数万円程度で補修することが出来ます。
しかし、ひび割れが大きくなり屋根材が欠けてしまっている場合や割れてしまっている場合には部分的に交換をする必要があり、そうなるとひび割れた箇所によっては近隣のスレートも剥がさなければならないため、費用が高くなる傾向になります。
つまり、一部破損したから部分的な交換にすると決めるのではなく、破損箇所や現状のスレートの状態によって、部分的に交換するのか、全面的に葺き替えするのか、カバー工法を使うのかを決めたほうが良いでしょう。
屋根材の色褪せ
色褪せは塗膜劣化の初期症状のサインで、スレート自体が水を吸ってしまう状態になってしまっています。
そのまま放っておくと屋根材の防水効果や保護効果が失われていき、上で紹介したひび割れや破損へと繋がってしまいます。
そのため、症状に気づいたら早い段階で塗装工事を行うことで屋根材を長持ちさせることができます。
スレート屋根は塗装によって屋根材を守ることで長持ちさせることができます。
屋根は外壁と比較して直射日光が当たりやすいことから紫外線や雨の影響を受けやすく、外壁と比較して色褪せ等の劣化の進行も早くなります。
屋根の色は自身の目で見ることが難しく、はしごなどで屋根に登ってチェックをするのも危険なため定期的に専門業者に見てもらうことをおすすめします。
陶器瓦・粘土瓦に発生する症状とメンテナンス方法
陶器瓦は日本の伝統的な家屋で使用されてきた屋根材で、耐火・耐水性に優れるほか粘土でできていることから防音効果にも優れます。
瓦屋根は素材が丈夫なため耐用年数は約50年と長く、表面には釉薬による膜があるため塗装の必要もありません。
一方で素材が丈夫な分、重量が重く耐震性の面では他の屋根材に劣ります。
基本的に新築時から陶器瓦を使用している場合には気にする必要はありませんが、新生瓦から葺き替える場合には注意が必要です。
屋根材のひび割れ
粘土瓦はスレート瓦と比較して丈夫ですが、飛来物による衝撃でひび割れが発生する可能性は0ではありません。
ひび割れが軽度なものであれば補修は可能ですが、耐久性が落ちるため新しい瓦に部分的に交換する事もできます。
粘土瓦は1枚あたり2.7~3.6kg程度の重量があり、瓦が割れて落下した際の被害も大きいため割れを見つけたら早めに専門業者まで依頼するようにしましょう。
漆喰の剥がれ
漆喰とは粘土瓦の隙間を埋めることで雨水の侵入を防いだり、地震などで瓦の位置がズレるのを防止してくれる重要な役割を持ちます。
そんな漆喰は粘土瓦に比べて耐用年数が短く、補修が必要になるケースがあります。
漆喰が剥がれてしまった場合、雨風によって棟に使われている台土が流れ出てしまったり、漆喰が機能しないことで瓦がズレ、雨漏りへと繋がってしまうケースが考えられます。
症状が雨漏りまで進行してしまうと瓦の修復だけでなく屋根の下地にも手をつける必要が出てしまい、費用がかさむため定期的に点検や詰め直し補修を行うことで予防していきましょう。
セメント瓦に発生する症状とメンテナンス方法

セメント瓦は別名プレスセメント瓦、コンクリート瓦などと呼ばれ、セメントと川砂を混ぜ合わせて作った屋根瓦です。
また、以前は日本モニエル株式会社が圧倒的シェアを誇っていたため、「モニエル瓦」と呼ばれることもありますがこちらもセメント瓦の一種です。
塗膜の色褪せや剥がれ
セメント瓦は陶器瓦とは異なり水分を吸収しやすいため定期的な塗装工事が必要です。
色褪せは初期症状のため色褪せが確認できた場合には塗装工事を考え始め、塗膜が剥がれて防水性能が無くなる前に塗装をするようにしましょう。
塗膜の劣化が進行するとセメント瓦の表面に残っている水分が原因でカビやコケが発生します。
初期であれば洗浄することでこれらは落とすことはできますが、カビやコケの発生は防水機能が失われている証拠のため、早めに専門業者に見てもらうことをおすすめいたします。
\お家の状態が一目でわかる報告書を作成/
ガルバリウム鋼板・ジンカリウム鋼板に発生する症状とメンテナンス方法
ガルバリウム鋼板とジンカリウム鋼板は表面をメッキ加工した金属製の屋根材です。
アルミニウムが持つ耐食性と亜鉛の防食作用により、金属素材の中でも特にサビにくく、防水性も備えているのに加え価格が安く、コストパフォーマンスが高い素材かつ軽量なため耐震性の観点でも優れます。
耐久性に優れているものの屋根材自体は金属製のため定期的にメンテナンスを行わないと錆びが発生してしまうことがあります。
屋根材の錆び
前述通り金属製が故にガルバリウム製の屋根材には錆びが発生してしまうことがあります。
強風が原因で飛来物がぶつかることで傷がついてしまったり、塗膜が剥がれることで防水効果が失われ錆びてしまうほか、積雪や塩害が原因となることもあるため定期的な点検は欠かせません。
メーカーは1年に1度の水洗い、5年に1度の点検、10年毎に再塗装などのメンテナンスを推奨しているように定期的にチェックをすることで屋根材本来の耐久性を損なわず長持ちさせるようにしましょう。
点検をした際に汚れを発見した場合、高圧洗浄や硬いブラシでゴシゴシ擦ってしまいがちですが、これらの行為はかえって塗膜を傷つけてしまう可能性があるため水洗いを行い、それでも落ちない場合は軽くこする程度にとどめておきましょう。
屋根塗装を行う場合はまずは表面をしっかりと洗浄します。その後、表面がつるつるとした金属板のため専用のプライマーを使って下塗りを行う必要があります。
すでに錆びが確認できた場合には錆び止め効果のあるプライマーも併せて使用することで進行を抑えます。
アスファルトシングルに発生する症状とメンテナンス方法
アスファルトシングル屋根は主に北米で広く利用されており、ガラス基材にアスファルトを浸透させ、砂粒・石粒で表面を仕上げている屋根材です。
一般的な屋根瓦やスレートヤエンと比較してその重さは半分以下となり、軽いため耐震性に優れています。
それ以外にも表面が石や砂ですので防音性も高く、また素材としてはアスファルト・防水シート・石や砂で出来ているため、割れやサビにくいという特徴があります。
表面や屋根材の剥がれ
アスファルトシングルは表面に石や砂を貼り付けているため、この石や砂が落下していまうことで、表面の剥がれが発生します。
また、アスファルトシングルでは施工の際に釘と接着剤を使用し固定しており、屋根材自体も軽いため、強風に弱く、浮きや剥がれが起こることがあります。
表面の剥がれについては屋根塗装を行うことで、メンテナンスを行うことが出来ますが、その際は油性の塗料を使用してしまうと、美観性・耐久性が低下してしまうため、水性の塗料で塗装を行います。
屋根材自体の浮きや剥がれに関しては、該当箇所の周辺をキレイに清掃し、接着剤を使用し再び固定することが可能です。
浮きや剥がれの箇所が多い場合には屋根カバー工法や屋根の葺き替えが必要になります。
カビや苔の発生
アスファルトシングルは湿気に弱い性質を持つため、屋根が日差しが当たらない北側にある場合や湿気がこもりやすい地域ではカビや苔が発生しやすいです。
カビや苔自体は高圧洗浄を行うことでメンテナンスを行うことが出来ますが、高圧洗浄により表面の石や砂が剥がれたり、ダメージが大きい場合はカバー工法や葺き替えが必要になる可能性もありますので注意が必要です。
屋根メンテナンスを行う時期
屋根のメンテナンスは築何年くらいから考えるべきでしょうか?
本項では屋根のメンテナンスを行うタイミングについて紹介していきます。
メンテナンスサイクルは屋根材や使用した塗料によって異なりますのでそれぞれの適切なタイミングで行うのが基本です。
初期費用は高くなりますが遮熱、断熱塗料は屋根表面の温度が上がりにくく、屋根材の熱によるダメージを軽減できるなどの効果もあるため塗料を選ぶ際の参考にしてください。
陸屋根の耐用年数とメンテナンス
陸屋根の場合はシートを張るシート防水とウレタンやFRPを使用した塗膜防水に分けられます。
それぞれ使用しているシートや塗料の耐用年数によって変化しますが、10年を目安に点検を行うなど定期的にメンテナンスを行いましょう。
ベランダやバルコニー、屋上のように上に立つことを前提に設計されている場合には表面がひび割れていないか、シートが破けていないか、雨天時に水が一箇所にたまらずにしっかりと排水されているかを確認するようにしましょう。
上に立つことを想定されていない場合には傾斜がないからと言って安易に登るのではなく塗装屋など専門業者に依頼して見てもらうのもおすすめです。
スレート屋根の耐用年数と塗り替えタイミング
スレート屋根の耐用年数は一般的に20年~25年ほどとされています。
しかし、これはあくまで屋根材の耐用年数であり、塗膜で保護されている事が前提のため、塗り替えを行わない場合には当然寿命は短くなります。
塗料の耐用年数は使用する塗料の種類によって異なりますが、屋根の場合は5年~10年に一度は塗り替えを行うのが望ましいです。
粘土瓦の耐用年数と塗り替えタイミング
粘土瓦の耐用年数は非常に長く、50~100年ほどと言われています。
粘土瓦の場合は塗装工事を行う必要がありませんが、漆喰が劣化していないかを10年に一度は点検しておくのがおすすめです。
塗装工事が必要ないかわりに粘土瓦の場合は劣化に応じて葺き替え工事が必要になります。
セメント瓦の耐用年数と塗り替えタイミング
セメント瓦の耐用年数はだいたい30年前後とされています。
耐用年数は比較的長いものの、材料の性質から塗膜が剥がれてしまうと他の素材よりも劣化が早く進行してしまうため注意が必要です。
こちらも塗料の耐用年数は使用する塗料によって異なりますが、5年~10年に一度は塗り替え、点検を行うのが望ましいです。
ガルバリウム鋼板の耐用年数と塗り替えタイミング
ガルバリウム鋼板の耐用年数は長く、30年~40年とされています。
塗り替えの目安も10年~15年と比較的長く、錆びや塩害が気にならなければメンテナンス期間も長めです。
トタン屋根の耐用年数と塗り替えタイミング

トタン屋根は最近では見かけることも少なくなりましたが軽量で加工のしやすい屋根材で、耐用年数も30年~60年と長めです。
しかし軽量故に衝撃に弱い点が問題です。
また金属製のため塗膜が剥がれた箇所や傷から錆びが一気に侵食する恐れがあり、定期的な点検と5年を目安に塗装を行うようにしましょう。
防水シートのメンテナンス
防水シートは屋根材の下に敷くことで屋根材だけでは防げない水から家を守ります。
防水シートはルーフィングとも呼ばれ、素材や機能によってさまざまな種類がありますが、耐用年数はアスファルトのもので10年~20年ほど、高耐久のものや透湿、遮熱機能があるものの場合50年とされているものもあるため新築時に使用されたものを調べ、時期に合わせたメンテナンスを行いましょう。
大雨の際には屋根材だけで防げない雨水を守るために防水シートに負担がかかります。
大雨のときにいつも雨漏りがするという場合にはシートが破損していることも考えられるので早めに業者に見てもらうようにしましょう。
\お家の状態が一目でわかる報告書を作成/
外壁のメンテナンス方法
本項では外壁材のメンテナンス方法を解説していきます。
外壁材によって耐用年数や劣化の原因が変わるためご自身のお住まいに使用されている外壁材の知識をつけ、素材にあった適切なタイミングでメンテナンスを行いましょう。
窯業系サイディングに発生する症状とメンテナンス方法

窯業系サイディングとは、セメントや繊維質を原料とした外壁材で、現在の日本では多く使用されているサイディングです。
素材の性質から耐火性に優れ、デザインも豊富ですが防水性に乏しいため塗膜が剥がれる前に外壁塗装を行いたいです。
外壁の色褪せ
塗装直後に比べて色が褪せてきたと感じたら塗膜の劣化を疑いましょう。
実際に手で触ってみると手に白い粉のようなものが付着するチョーキングと呼ばれる現象が発生することがあります。
チョーキングは初期であれば白い粉が手に付きますが、その状態でしばらく放置していると外壁の色が手につくようになります。
どちらの状態も塗料による保護効果が失われている状態ですので塗り替えを検討しましょう。
コケや藻の発生
コケや藻は外壁表面の塗膜が劣化し、防水性が弱くなっている証拠です。
特に日当たりの悪い北側で発生しやすいため注意して見てみましょう。
そのままにすると劣化が進行するため、初期であれば定期的に掃除をしてコケや藻を除去しましょう。その際にしっかりと水気を切るのが重要です。
何度も発生するようであれば塗膜が剥がれている可能性が高いため外壁塗装を検討しましょう。
ひび割れ(クラック)の発生
窯業系サイディングの場合は珍しいですが、外壁にひびが入っているのも劣化症状のひとつです。
0.3mm以下の細いヘアクラックであれば塗膜表面のひびの可能性が高く、コーキングなどの補修で済むことが多いです。
一方で構造クラックと呼ばれる深いひびの場合は早急に対処が必要です。
多発している場合には外壁材のカバー工法や張り替えを検討する必要があるため専門業者に相談しましょう。
金属系サイディングに発生する症状とメンテナンス方法
金属系サイディングはガルバリウム鋼板などの比較的耐久性があり、腐食にも強い外壁材です。
外壁の色褪せ
塗装直後に比べて色褪せてきたと感じたら塗膜の劣化を疑いましょう。
実際に手で触ってみると手に白い粉のようなものが付着するチョーキングと呼ばれる現象が発生している場合があります。
症状が確認できるようであれば塗り替えを検討しましょう。
傷や錆びの発生
金属系サイディングは比較的強度が高い素材ではありますが硬いブラシでこすったり、強風による飛び石などが原因で傷がついてしまうことがあります。
この傷が原因で外壁材に直接水分が付着することで錆びが発生します。
錆びが発生している場合は丁寧に錆びを除去した後で防錆効果のあるプライマーを用いて下塗りをし、上塗りを行います。
金属系サイディングの場合は有機溶剤系の塗料を使用すると腐食や変色の原因となるため使用しないようにしましょう。
樹脂系サイディングに発生する症状とメンテナンス方法
樹脂系サイディングは聞き慣れない方も多いと思いますが、塩化ビニル樹脂を原料としたサイディングボードで、塗装やボード同士を繋ぎ合わせるシーリングという作業が必要ないのが特徴です。
通常ボードを繋ぎ合わせる際に使用するコーキングを使わないため、目地の劣化が発生しません。
亀裂の発生
樹脂系サイディングはボード自体に顔料が含まれているため外壁塗装を必要としないケースが多いです。
そのため、亀裂が発生した場合は劣化状況に合わせてカバー工法で重ね張りを行うか、既存のボードを撤去して張り替えを行います。
木質系サイディングに発生する症状とメンテナンス方法
木質系サイディングは、その名の通り木材で作られたサイディングで、無垢材の表面を加工することで防火性や耐久性を高めています。
木材ゆえに腐食に弱く、きちんとメンテナンスを行う必要があります。
コケや藻の発生
コケや藻は外壁表面の塗膜が劣化し、防水性が弱くなっている証拠です。
特に日当たりの悪い北側で発生しやすいため注意して見てみましょう。
外壁の反り
木質系サイディングは天然木を使用しているため、塗膜が剥がれ防水性が失われると水分を含みやすい材質です。
木は水分を含むことで変形しやすく、外壁が反ってしまうことがあります。
変形が激しい場合は外壁材を張り替える必要性が出てくるので定期的にメンテナンスをして長持ちさせましょう。
モルタル外壁に発生する症状とメンテナンス方法

モルタル外壁は職人が直接壁に塗って仕上げる外壁材で、粒を吹き付けた「リシン仕上げ」や、漆喰を5~10mmの厚さで吹き付けた「スタッコ仕上げ」、コテの跡を残した「左官仕上げ」などデザインの自由度が高いのが特徴です。
コケや藻の発生
コケや藻は外壁表面の塗膜が劣化し、防水性が弱くなっている証拠です。
特に日当たりの悪い北側で発生しやすいため注意して見てみましょう。
そのままにすると劣化が進行するため、初期であれば定期的に掃除をして除去しましょう。その際にしっかりと水気を切るのが重要です。
何度も発生するようであれば塗膜が剥がれている可能性が高いため外壁塗装を検討しましょう。
ひび割れ(クラック)の発生
モルタル外壁は直接職人が仕上げることから腕による差が出やすく、ひび割れが発生しやすい外壁材です。
モルタル外壁と密着しやすいプライマーを用いてクラック内部にもしっかりと補修を行う必要があるため、ひび割れを見つけたら早めに相談するのが良いでしょう。
外壁メンテナンスを行う時期
外壁のメンテナンスは築どれくらいが目安でしょうか?
外壁のメンテナンスタイミングは素材によっても異なりますが、基本的には使用した塗料に応じて点検、塗り替えを行う必要があります。
窯業系サイディングの耐用年数と塗り替えタイミング
窯業系サイディングのメンテナンスは7~10年を目安に行うことが一般的であるものの、つなぎ目に使用されるコーキング材が劣化しやすく、5~10年でメンテナンスが必要になります。
金属サイディングの耐用年数と塗り替えタイミング
金属サイディングは軽量で水に強いためひび割れも発生しづらく、メンテナンス周期は10~15年とされています。
しかし、他のサイディング同様つなぎ目(目地)のコーキングの早期劣化には注意が必要です。
ALC外壁の耐用年数と塗り替えタイミング

軽量気泡コンクリートを用いたALC外壁は症状が出る前にメンテナンスを行うのが重要な外壁材です。
気になる箇所がない場合でも5年を目安に定期点検を行うようにしましょう。
屋根や外壁のメンテナンス業者を選ぶコツ
外壁や屋根のメンテナンスはしっかりと業者を選ばないと、悪質な業者による被害はもちろん、そもそも満足のいく施工ではなく、悲しい思いをしてしまう可能性もあるため、メンテナンス業者を選ぶ時は必ず以下のポイントをチェックしましょう。
- 施工実績数はどのくらいあるか
- 保証内容やアフターフォローは充実しているか
- 職人やスタッフの資格はあるか
施工実績数はどのくらいあるか
信頼できる業者を選ぶためには、施工実績数は参考になる指標の一つです。
ホームページ内にある「お客様の声」や「施工事例」は実際に職人が行なった施工の結果ですので、その質はもちろん、その数が多いほど知識や経験が豊富にあると考えられます。
もちろん、店舗や営業所の数や対応エリアによって数は基準は異なりますが、施工実績が公開されていないような業者はそもそも利用者のために参考になる情報を掲載していないため、実際の施工時でも利用者のために細かい気配りができない、等の可能性もあります。
そのため、施工実績が公開されているか、またその数は豊富にあるかなどは確認しておきましょう。
保証内容やアフターフォローは充実しているか
充実した保証やアフターフォローがあるのは優良業者の特徴の一つです。
外壁塗装の保証制度には以下のようなものがあります。
| 自社保証 | 外壁塗装業者が独自に運営する制度です。保証期間中に外壁塗装業者が倒産すると、アフターフォローを受けることができません。 |
| 第三者保証 | 外壁塗装業者の加盟する組合・団体が運営する制度です。外壁塗装業者が倒産しても、組合や団体によるアフターフォローを受けられることがあります。保証期間や内容は加盟組合・団体によって異なるため、契約前の確認は重要です。 |
| 塗料メーカーによる保証 | 一部の塗料メーカーが運営する制度です。対象地域や対象塗料の種類などの条件が厳しく、一戸建ての外壁塗装で適用されることは少ない傾向があります。 |
そのため、メンテナンスを依頼する前に、その業者は保証やアフターフォローがあるか、また、その内容はどのようなものかを必ず確認しておきましょう。
職人やスタッフの資格はあるか
外壁塗装を行うために特別な資格や免許はありませんが、技能や経験の高さを証明するような資格や大規模な工事を行うための許可証は存在します。
例えば、「塗装技能士」という塗装技術を認定する国家資格があり、1級の合格率は約40%と、職人の中でも技術力がしっかりとある人がこの資格を取得しています。
もちろん、塗装やメンテナンスの仕上がりや技術力によって決まるため、筆記試験をクリアした塗装技能士でも実際にしっかりとサービスを提供できるのかはわかりません。
そのため、スタッフの資格有無だけで判断せず、その他のチェック項目や相見積もりなどによって、金額や職人・スタッフの丁寧さなども加味して判断するのが良いでしょう。
業者選びのコツについてはこちらの記事でもご紹介していますので参考にしてください。
外壁塗装の優良業者の探し方と選び方のコツ 大手と地元企業の違い
メンテナンスをしないとどうなる?
メンテナンスを定期的に行わないと家が教えてくれた劣化症状に気づくのが遅くなります。
家が早く傷んでしまうのはもちろんですが、劣化が原因で瓦やタイルが落ちてくると怪我をする可能性もあります。
屋根も外壁も劣化が進行する前であれば比較的簡単な補修で済ませることができます。
簡単な補修で済むということは費用も抑えることができるので経済的にもお得です。
劣化が進行する前であれば部分補修で済んでいた内容でも、放置してしまったことで劣化が進行している場合は施工箇所が増えるため工期も伸び、金額もかさみます。
そうならないために定期的に点検を行い、予算内で安全に暮らせるようメンテナンスを行いましょう。
三和ペイントでは無料点検サービスを実施中!!
現在三和ペイントでは外壁や屋根の点検を無料で行っております。
社内の厳しい研修、試験を受けて認定された住宅塗装点検者があなたのお住まいを隅々まで徹底的に点検いたします。
点検した92項目それぞれの結果はいつでも見返せるようにわかりやすく資料におまとめしますので今後のメンテナンスプランにご活用ください。
\お家の状態が一目でわかる報告書を作成/